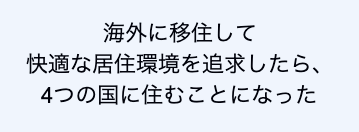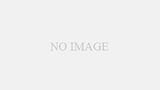その人は、今後生き残っていくために、日本の伝統を引き継ぎながら物作りに励んでいくということで今は修行に励んでいるが、実際のところ販売についてはこれまでのやり方を踏襲しているだけで、これといってマーケティングについて何も知っているわけではないし、今後どういったことに取り組もうといったことを考える段階にもいない。
ある意味で、弟子になるということは、物作りについての制作技術を受け継ぐことはできるものの、販売についてプロから教わる機会を持つことは非常に少ない。
そもそも工芸品に限らず、売る技術はものづくりとは別物という扱いなので。
その結果として何が起こるのかというと、たとえ良い商品を作っていたところで買い手が付かず、結局売上がたたず、利益も出ないという状況。
これは焼き物だけではなくて、様々な伝統工芸品において、今現在見られることなのは周知のとおり。
着物にしてもそうだし、それ以外の多くの伝統工芸品も日本人に対してはそれほど需要がなくなってしまっている。
喜んで買ってくれる人に工芸品を売る、あるいは情報を届けることについて様々な試みが行われてきたものの、結局売上の低下に大きな歯止めがかかることもなく、今に至る。
世界の市場を視野に入れると
日本の小さなパイの中で商品の販売を頑張っていくよりも、Facebookページを作るなり何なりして海外に売っていった方が、実を言うと圧倒的に大きな市場があるし、裕福でなさそうな国であっても、意外に中流階級以上はお金を持っていたりもするので、ある程度値段を高く設定しても売れたりする。例えば、マレーシアやフィリピン、あるいはタイといった国は、日本人からのイメージからすれば決して豊かではない印象がある。
そんな国に高級品が売れるのだろうかと、疑問を持つ人も少なくないだろう。
しかしながら、彼らの中にもお金持ちはいるので、一つ数万円から数十万円の茶碗が売れることもあるし、あるいはディスプレイ用に高額な着物が販売されることもある。
実際、ジョホールバルのプレミアムアウトレットというショッピングモールにある日本料理屋・勘八においては、立派な着物が店の入り口の左手に飾ってある。
他にも様々な例が日本工芸堂さんのサイトで紹介されている。
こういったこともあるので、例えばわかりやすいところであればFacebookページでとりあえず広告を打って集客をして、そこから工芸品の販売に繋げるとか、あるいはeBayや海外のアマゾンで商品を出品してそこから販売をするとか、そういった手軽なところから始めてみるのも一つの方法。
特にeBayやアマゾンの場合であれば広告費をかけずにスタートすることができるので、どの商品が売れるかというリサーチをすることもできる。
外国人に受け入れてもらえる日本の伝統工芸品ということで考えれば、実を言うと潜在的に様々な商品が当てはまる。
場合によっては、自分で物を作るだけではなくて、同業者から商品を委託販売する形にして、注文が入ってから発送をするとか、もしくはその発送作業も作り手の工房等にお願いするとか、そういったこともできるので、この分野には実はかなり可能性があると思っている。
在庫を処分するチャンスも
外国人の好みは日本とはまた違うので、売れ残った在庫が解消できる場合もある。海外を相手にする場合には、日本好きのお客さんの開拓になっていくことが多いため、自分が作った工芸品だけを売るよりは、ある程度商品のラインナップを広げた方が有利。
外国人とコミュニケーションを取れる能力があれば、パイプも作りやすい。
日常的な英会話がだめでも、メールでやり取りができればいいわけで、難易度はさほど高くはない。
そう考えると、周囲の同業者、あるいは近い業界をライバルや競合と捉えるよりは、同じく日本の伝統を体現する仲間としてやっていく方が長期的には有利だろう。
もっとも、そうなってくると、もはや作り手が片手間でやるよりも、販売専門の担当者を社内に置くとか、外部のマーケターに依頼した方が効率的な気がするが。
海外に移住するのは本当に難しいのか?

日本を出て海外に住むようになってから
「海外に移住したい」という話をよく聞くようになった。
同時に、
「英語が苦手で・・・」
「海外での部屋選びで失敗しないか不安」
「他の国での生活を想像できない」
「下見で何を確認したらいいか分からない」
「移住後の仕事やお金が問題」
等々の様々な不安や悩みも耳にする。
そこで、10年以上海外で暮らし、
4ヵ国に住んできた経験を凝縮した電子書籍、
『「いつか海外に住みたい」を手の届く現実にするための本』
を無料でプレゼントすることにした。
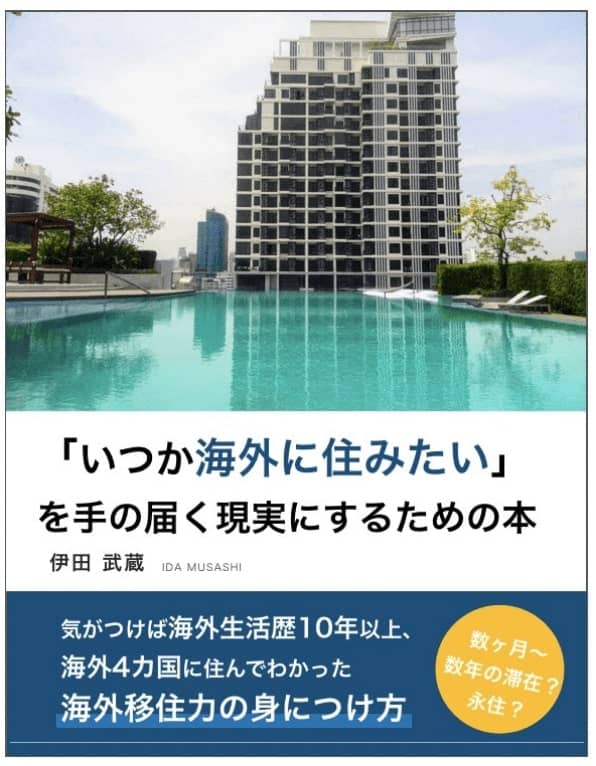
電子書籍の目次等も掲載しているので、
プレゼントページへどうぞ。
電子書籍のプレゼントページへ