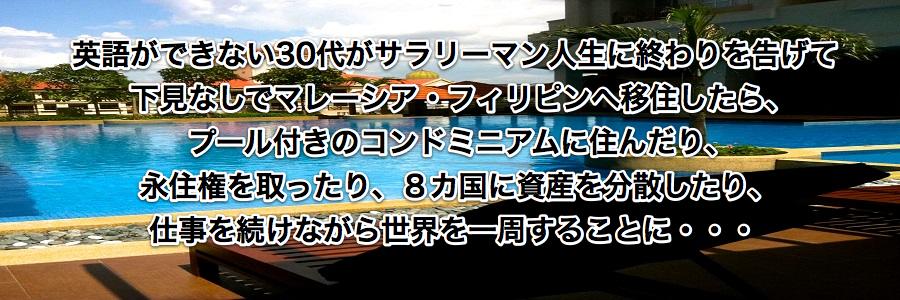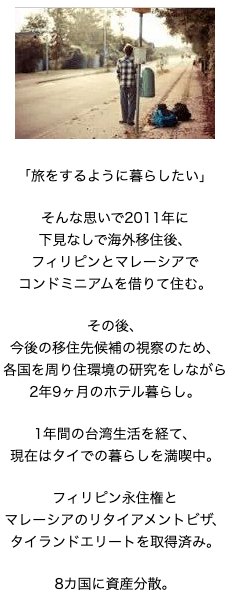ホテルの最寄り駅であるヴィシェフラド駅から目的地へ行くまで、途中でメトロを乗り換えて移動することになった。
駅に着いたとたんに電車が滑り込んできたので、とりあえず乗らないと見逃してしまうが、進行方向がどちらなのかわからず、私が向かう方角という確信はなかった。
プラハのメトロはなかなか不便で、あちこちに進行方向への表示があるわけではなく、広いプラットホームに2ヶ所ぐらいしか表示がない。
表示まで近づいていかないと、どちらの方向に進行していくのか、地元の人でもないとわからない。
とりあえず、1/2の確率だと思ってギリギリで乗り込んでみたところ、真逆の駅に行ってしまった。
結局次の駅で降りて乗り換えたので、それほど時間をロスしたわけでもなく、おそらくどちらにしても同じ電車に乗ることができたのでよかったと言えばよかったが、乗り換え駅でも全く同じシチュエーションになって、こちらもとりあえず目の前にきた電車に乗ってみたら、不運なことに反対側の方向に動いてしまった。
2回連続で失敗する確率は1/4なので、十分に起こり得る確率ではあるものの、そこそこ運が悪い感じになってしまった。
海外で駅の表示が分かりづらいことは日常茶飯事
駅の表示が分かりづらいのはチェコに限ったことではなくて、各国で同じような状況が基本的に確認できる。逆に言うと日本のようにどちらに進んで、なおかつ次の駅がどこであるとか、そういった表示を親切にしてくれて、駅の中の至る所に表示があるような国の方がむしろレアであるということも、いろんな国を見ているとわかる。
しかしながら、これだけグローバル化が進んでいる時代において、他の国から旅行者が来ることは日常なわけだし、別に末端の職員までそういった習慣が浸透していなくても、上級職員が他の先進国に行ってわかりやすい表示を見て、それをただ単に真似をして導入するといった模倣は容易なはず。
その割にこういった改善が起こらないのは、やはりインフラ事業に顧客志向のサービスが根付くモチベーションがないのかもしれない。
特に鉄道は飛行機以上に新規参入が難しい業種で、新しい競合企業が入ってくることもなければ、古い会社の採算が取れなくて撤廃という例もそこまで多いわけではない。
さらに言えば、不採算事業の鉄道もただ単に表示を改善すれば採算が取れるようになるとか、そういう話ではない。
むしろ立地や、駅周辺に住んでいる人の人口減少とか、そういった要因による影響の方が大きいので、はっきり言って表示が不親切であろうが、関係なく顧客を獲得できるビジネスモデルになってしまっている。
こういった背景を鑑みると、残念ながら、顧客サービスという志向性が働かなくてもやむを得ない部分はあるし、期待することができない業種でもある。
インフラ事業において前時代的な顧客対応をされていたとしても、驚くことではないのは、各国に共通する事情と言える。