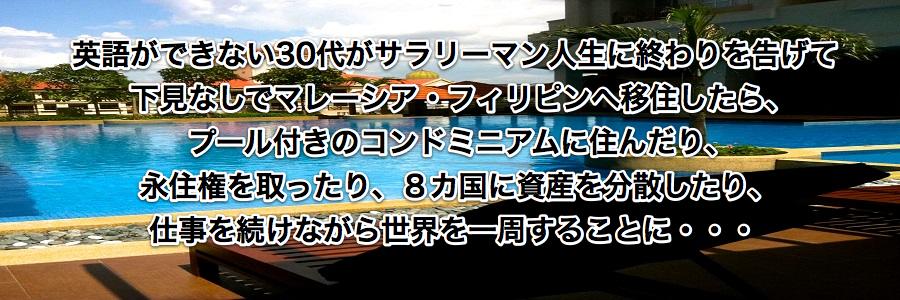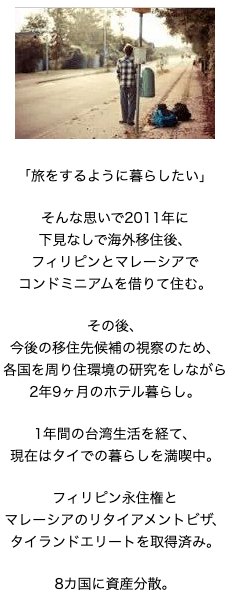いかに緻密な計画を立てて綿密なシミュレーションを行い、リスク管理や目標達成を計算するかを重視する人たちもいる。
世の中の一部の職業においては、それができなければ信用を得られず、そもそも仕事を受注できない場合もある。
例えばコンサルの場合であれば、よほど顧客の信用を得ていない限り、提示する計画が勝負だったりするので、そういった場合であればやむを得ないところもある。
しかしながら、自分の人生においてまで、綿密に計画を立てる必要があるのかということになると、それはかなり疑問がある。
特に、未知の分野にどんどん進んでいく場合、自分の知識や経験は未来に向けて増えていくわけで、以前は盲点だったところが、当たり前のように視界に入るようになってくる。
言ってみれば、レベル5の時には見えなかったものが、レベル9に上がった時には、当たり前の事実として認識できるようになる。
そうなってくると、レベルが低かったころに作成した計画は、とても幼稚で稚拙なものに見えてきてしまう。
そうなった時には、当然ながら修正が必要になってくるわけで、知識や経験のレベルが上がっていくスピードが早いと、もはや計画は暫定的な一応のプランであって、その通りに進むことは初めから想定することができなくなっていく。
ということは、細かいところまで考えるよりも、大まかなグランドデザインだけを考えておいて、随時方向性を修正していくことになる。
海外に出て選択肢が増えた
例えば、私の場合、海外生活を始めるまでは、ろくに旅行に行ったこともないくらい、日本国内に引きこもっていた。そんな状態で今の生活を想像できたわけもなく、マレーシアに2年間住んだり、フィリピンに引っ越したり、その後は世界一周をしたりしている間に、どんどん選択肢が広がっていった。
当然ながら、1年前や2年前には手にしていなかった選択肢も数多く出てくるわけなので、過去の自分の決定にいちいちとらわれている意味もない。
そして今後の計画を考える際にも、いくつかの選択肢と、それぞれについてのシミュレーションはするものの、最終的な決定は、いつも最新の状態で判断を下すようにしている。
つまり、今日の私よりも3ヶ月後の私の方が判断のレベルは上がっているはずだし、今は3つしか選択肢がなくても、4つ目、5つ目の選択肢が出てくることもある。
そして、その新しい選択肢は、既存のものよりもどう見ても優れている場合もあるので、机に座ってパソコンの前でマインドマップに色々なことを書き出してみても、それはせいぜい頭の整理に繋がるぐらいで、最終的には走りながら考えていくことになる。
どこかのタイミングで立ち止まって思考をするのではなくて、サッカーのように常にピッチ上を動き回りながら、変化していく状況に応じて、その場その場に合った判断をしていくイメージ。
潜在的な最短ルートを探す感覚
根本にある方向性さえ決まれば、あとは個別に決断を下していくというよりは、本来自分が進むべき道を見つけていく感覚に近くなっていく。元々、抵抗なく進みやすい道は決まっていて、それは世界の状況によって、本来的に与えられたもの。
一個人として努力をしたところで、その道以外を行ってもあまり効果は得られない。
それは大海原において、人間が潮の流れに逆らって必死で泳ぐよりも、海の流れにそって、潮流を読みながら身を任せる方が楽で理にかなっているのと同じこと。
それはある意味で言うと思考放棄に見えるのかもしれないが、実際は現在地とゴールを結ぶベストなルートを模索しているにすぎない。