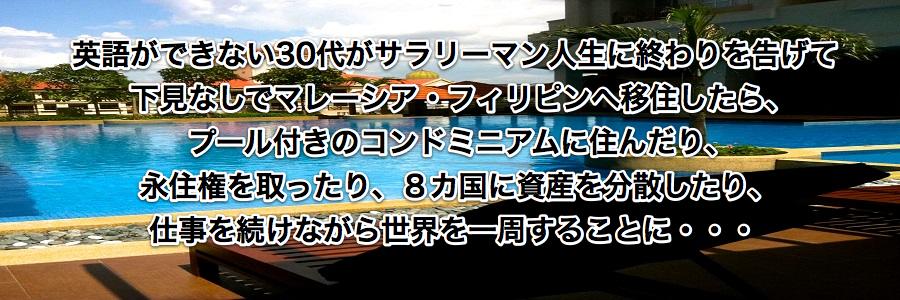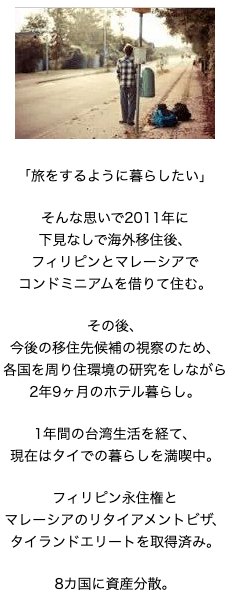中国本土やマカオ、香港の午前中によく見かける光景がある。
それは、大勢の人が集まって、太極拳やその他の体操をしている姿。
香港の九龍公園でもいくつものグループを見かけたし、マカオでは海沿いで太極拳の演舞をしている人たちを見かけた。
もちろん中には一人でやっている人もいる反面で、大多数は集団で行っている。
グループの人数はまちまちで、五人くらいで行っていることもあれば、20人ほどの団体の場合もある。
一人の指導者というか、インストラクターのような人が前で他の人達と向かいあって対面になる形で踊っていることもあるし、特にリーダーらしい人が見受けられない場合もある。
なんにしても、孤独な老後という言葉からは、かなり遠い印象を受ける。
今朝も一點心で朝食を取ろうと思って出かけたら、やはり太極拳をしている団体を見かけた。
こういったわかりやすい地域のコミュニティがあるのは、孤独を遠ざけるためには非常に有効な手段となる。
コミュニティによる人とのつながり
孤独が絶対的な悪としてみなされる必要はないにしても、寿命を縮めるという数々のレポートも出ているし、老人が孤独死することになれば、本人が困るとか家族が悲しむだけではなくて、住んでいる家の所有者にも迷惑がかかるし、死後何日も立ってから見つかったような場合だと清掃業者にとっても大きな負担になる。そういったことを考えると、老後になるほど他人との関わりが本人にとっても社会的にも重要なライフラインとなる。
ただ単に水道やガス、電気といったものだけがあれば人間は満足に暮らしていけるわけではないし、最終的に命の終りを迎える際にも周囲との関係性は重要で、猫や象のように人知れずひっそり姿を消すというのは現実的ではない。
そう考えてみると、香港やマカオのわかりやすいコミュニティの形成は、ある部分では非常に望ましい。
ではこういうものを日本に取り込んでみてはということになると、なかなか難しいところもある。
日本版の高齢者コミュニティ
もし仮に早朝にラジオ体操をやろうと呼びかけても、おそらくは日本人の高齢者層を呼びこむことはできないと思われる。せいぜいそんなことをしているのは夏休みの小学生くらいで、それ以外の世代をラジオ体操をしに集めることはなかなか難しいし、かといって太極拳やカンフーといった全く馴染みのない運動をいきなり始めようといっても、聞く耳を持つ人は限られているだろう。
かといって、日本人に馴染みのあるボクシングや空手の動作をゆっくりやれば、それでコミュニティに参加したい人が集まるかといえば、それも甚だ疑問なところで、健康的な集まりを見つけることはなかなか難しい。
例えば、一緒にウォーキングをするとか、ハイキングに出かけるとか、そういったサークルは考えられるし、以前に高尾山に登ったときには、50代や60代、さらには70代と思われるような登山者がグループで登っていたが、こういったこともなかなか日常的に行うことは難しい。
ちなみに高尾山はスーツで登っているサラリーマンもいるくらい気軽に登れるし、山というべきか丘というべきか迷うレベルではあるが、本格的な登山着で登っている人も多数いた。
病院に集まる高齢者
では、こういった中で日本人の高齢者がどこに集まっているかということを考えると、その一つが病院の待合室になっている。この点については、医療費の増大による財政圧迫の面からも、以前から懸念の声が上がっており、大した体の異常もないのに病院に来るお年寄りが増えることで、本当にすぐに治療を受けなければいけない人や検査を受けるべき人も待ち時間が長くなって、不利益を被る弊害もでている。
地方創生というスローガンを掲げるのであれば、こういった問題を解決してコミュニティをうまく作っていくのも一つの方策となる。
しかしながら、地方自治体としてほしいのは納税者の世代というのがかなりの部分での本音であり、ケアの必要な高齢者を積極的に呼び込むことは、却って財政赤字を膨らますことにもなりかねないので、なかなかそういったところに力を入れづらい実情もある。
しかしながら、日本が世界に先駆けて高齢化社会に突入するということは、必然的に社会実験の場となるということ。
ここで積み上げたノウハウを外国に輸出することも将来的にはできるし、そういった部分を産業化してキャッシュポイントに変えることによって、長期的に見ると面白い自治体運営も可能になるかもしれない。